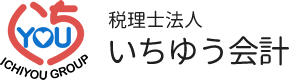確定申告で医療費控除を受けたい|対象者や申請手順を解説
医療費は一定の条件を満たせば確定申告を通じて医療費控除を受けることができます。
医療費控除を適用することで、所得税の軽減につながるため、医療費が多くかかった場合はぜひ活用したい制度です。
本記事では、医療費控除の対象者や申請手順について詳しく解説します。
医療費控除の概要
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで所得控除を受けることができる制度です。
控除の対象となる医療費
医療費控除の対象者は、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の医療費も含まれます。
対象となる費用は、診療費、入院費、薬代、通院のための交通費(タクシー代などを除く)などが該当します。
ただし、美容整形や健康診断費用(異常が見つかり治療を受けた場合を除く)などは控除の対象外となります。
控除を受けるための最低額
年間の医療費が10万円(または総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額×5%)を超えた場合に、超過分が医療費控除の対象となります。
医療費控除の申請手順
以下、医療費控除の申請手順を解説します。
1. 必要書類を準備する
医療費控除を受けるには、まずは領収書や医療保険者等が発行する医療費通知を整理し、年間(1月1日〜12月31日)の支払額を確認しましょう。
給与所得者の場合は、源泉徴収票も用意します。
2. 医療費控除額を計算する
年間の医療費の合計から、保険金などで補填された金額を差し引き、さらに10万円(または総所得金額が200万円未満の場合は総所得×5%)を差し引いた金額が、医療費控除額となります。
ただし、医療費控除の上限は200万円です。
3. 必要書類を作成・提出する
確定申告書と医療費控除の明細書を作成し、作成した書類を税務署の窓口、e-Tax(電子申告)などを通じて提出します。
医療費の領収書は提出不要ですが、税務署から求められた際に提示できるよう5年間は保管しておく必要があります。
医療費控除の注意点
医療費控除とセルフメディケーション税制(特定の医薬品の購入費用を控除する制度)は同時に適用できないため、どちらを適用するか事前に検討しましょう。
まとめ
医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に所得税の負担を軽減できる制度です。
対象となる医療費を把握し、必要な書類を準備した上で、適切に確定申告を行いましょう。
医療費控除について不安がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
愛知県
- ・本部事務所
- 〒488-0855 愛知県尾張旭市旭前町5-7-21 三浦ビル201
- ・中川事務所(総務担当事務所)
- 〒454-0841 名古屋市中川区押元町2-110
- ・名古屋西事務所
- 〒451-0066 名古屋市西区児玉2丁目23番15号
岐阜県
- ・岐阜事務所
- 〒502-0027 岐阜県岐阜市長良宮口町1丁目1番地
ピッケルツインピノ1階北
大阪府
- ・大阪事務所
- 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-9-20
新大阪GHビル902号室